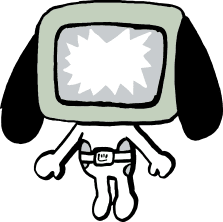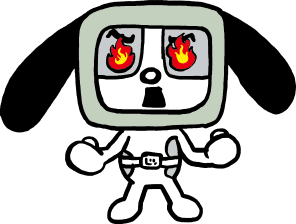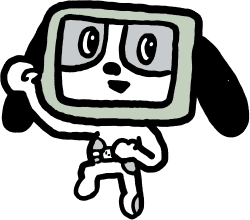こんにちは。
未来工作ゼミのハカセ。よーだです。
群馬県の新島学園中学校ではデジタル工芸教室と称して毎年全学年全クラスに対してプログラミング授業を行わせていただいています。
中学校3年生の技術科でプログラミング授業を行ってきましたので、その時の様子をレポートします。
BLOG
中学校技術授業でプログラミング!新島学園中学校3年生授業_2021年度前期レポート
たのしくSDGsを目指せる作品を作ろう!
ことに最近話題になるSDGsというものをご存じかと思います。”持続可能な開発目標”を指す言葉で「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」などの17の大きな目標とそれぞれに大した169の具体的なターゲットが設定されています。
学校でも公民の時間などで取り上げられているようで、特にSDGsの達成目標である2030を中心的に生きることになる若者たちの間でトレンドになっているように感じています。
小学校や中1の講座では自由なアイディアを形にすることを重視してどちらかというとより遊びに近いテーマを採用していましたが、中学3年生ではすこし社会課題へと目を向けて、SDGsを目指せるツールをプログラミングとキータッチを合わせて開発することをテーマに据えてみました。


ゴールに対して課題を洗い出し、アイディアを発想する
授業の最初には技術の時間で制作した木工作品”デジタルメモスタンド”に付箋とペンをセットし、チームに分かれて17の目標が抱える課題と、それを解決するためにはどうすればいいか?のアイディアを思いつくままに書き出してもらいました。
中学になってくるとこういった社会課題へ対しての関心も相応に高く、様々な課題が湧き出てきます。何をすればそれを解決できるのか、よい方向に向かっていけるのかをチームで話し合います。


考えついたアイディアを実現するための仕組みをプログラミングと技術で再現する
50分2コマの授業の中で課題とアイディアの話し合いをしてもらい、アイディアを実現するためにプログラムとキータッチを使った現実の入力を生かした工作物までを作ってもらいました。
なかなかに厳しいスケジュールでしたが、各チームでプログラムをする人、工作物を作る人、全体を監督する人など役割をもって分担してすすめました。実際に社会課題を解決するため、人に行動変容を促すためにはプログラミングだけでなく現実での動作やセンサーなどを利用することが必要になってきます。
冷蔵庫の模型を作ったり、募金を促すための装置をつくったりなどプログラミングと同じくらい工作物を作る技術力も必要になる時間でした。


むすび
様々に面白いアイディアがあふれた作品が形になりましたが、この日は完成させるだけで時間いっぱい。発表は次の時間となりました。
中学3年生では50分2コマの授業をそれぞれ3週にわたって実施します。次回は発表とそれを受けた作品のブラッシュアップを行う予定です。どんなアイディアが登場したのかまたレポートしたいと思います。

TOP